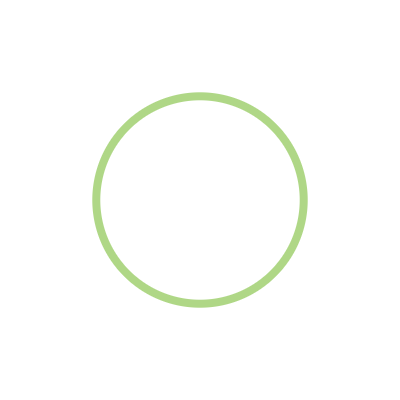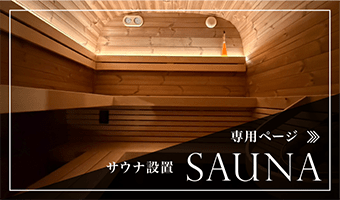床材の「重ね張り」で空間を一新
住まいのリフォームを考える際、床の張り替えは空間全体の印象を大きく左右する要素のひとつ。
中でも、近年のリフォームで注目されているのが「カバー工法(重ね張り工法)」です。これは、既存の床材を撤去せず、その上から新しい床材を施工する方法で、工期の短縮やコストの削減といったメリットがあります。
今回は、カバー工法を用いて無垢フローリングを取り入れるケースについて、施工例とともにご紹介します。

床を張り替えずにリフレッシュできるカバー工法
一般的に、床のリフォームと聞くと「既存の床材を剥がして、新しいものを張る」という工程を思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし、剥がし作業には手間も時間もかかり、廃材の処理費用も発生します。
それに対してカバー工法は、今ある床をそのまま下地として利用し、その上に新しい床材を施工する方法。

現場によっては一部段差処理などの工夫が必要になる場合もありますが、施工は比較的スムーズに進み、短期間で仕上がることが多いのが特長です。
もちろん、張り替えエリアの家具などを移動する必要はありますが、床材の撤去作業がない分、騒音や粉塵も軽減され、住みながらのリフォームも容易となります。
無垢フローリングもカバー工法で施工可能
「カバー工法」と聞くと、薄く軽い建材しか対応できないように思われるかもしれません。しかし、実は無垢フローリングを選ぶことも可能です。

無垢材のフローリングは、自然素材ならではの温かみと優しい肌触りが魅力です。素足で歩いたときの感触や、室内に広がる木の香りは、合板やクッションフロアにはない心地よさを生み出します。
今回の施工例では、既存のフローリングの上に、無垢材を重ね張りしました。
見た目も美しく、木の表情が空間全体をやさしく包み込むような印象に。ナチュラルで落ち着きのある雰囲気が生まれました。
下地の状態確認は必須
カバー工法を採用する際に、最も重要なのは「既存の床の下地がしっかりしているかどうか」です。たとえば、歩いたときに沈む箇所がある場合や、経年によって下地の合板が劣化している場合は、そのまま重ねると不陸(凹凸)が目立ったり、きしみや床鳴りの原因になったりします。
そのため、施工前には床下の状況確認をしっかり行い、必要に応じて補強を加えることが大切です。
特に無垢フローリングは、木の動きが出やすい素材でもあるため、施工の精度が重要となります。
また、カバー工法では床の高さが数ミリ〜1cmほど上がることがあります。引き戸やドアの開閉、巾木や段差との取り合いなども含めた納まりの確認も必要です。
見た目だけでなく「暮らし心地」も変わる
今回のように、無垢フローリングをカバー工法で取り入れることで、見た目が美しくなるのはもちろんのこと、実際の暮らし心地もぐっと向上します。

例えば、冬の朝。ひんやりした床に素足をのせたとき、無垢材ならではのやさしい温もりが感じられます。夏はさらっとした肌触りで、湿気もこもりにくいという利点も。住まいに自然素材を取り入れることで、空間に「呼吸」を感じられるような、そんな心地よさが加わります。
「カバー工法+無垢フローリング」は、手軽さと上質さを両立した、賢い床リフォームの選択肢のひとつ。
床の張り替えを検討中の方、費用や工期がネックになっている方、そして無垢材の心地よさを暮らしに取り入れたいと考えている方に、ぜひおすすめしたい工法です。
ちなみに・・・こちらのお宅では、フローリング工事と同時に、古くなってきた浴室及び洗面脱衣室もリフォーム!
【before 浴室】
【after 浴室】
【Before 洗面脱衣室】
【after 洗面脱衣室】
洗面脱衣室~浴室のバリアフリーも実現。使い勝手も向上し、ステキなお住まいに生まれ変わりました♪